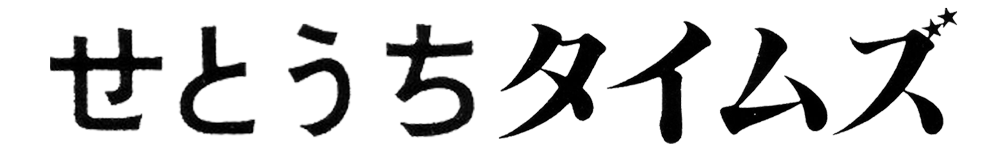ふるさとの史跡をたずねて【395】蔵本墓(尾道市因島重井町善興寺)
蔵本墓(尾道市因島重井町善興寺)
因島村上氏の因島退去後、柏原忠安の次男、三男が川ノ本家、蔵本家を始めたのが因島柏原氏の始まりだと記した。「クラモト家は二軒ある。どう違うのか?」と、しばしば尋ねられた。私は川ノ本家の方の末裔(正確には分家の分家)だから、知らなかった。蔵本という名前の由来も。
ある時、長右エ門家の墓を探していたら蔵本家の墓があった。その一つに「俗名蔵本」と書いてあるではないか=写真㊦。
狭い土地に同苗者が多いと苗字よりも名前の方が区別がつきやすく多用される。その多くが屋号として固定化される。
その同じ屋号が二軒あるというのである。正確には漢字が異なり「倉本」と書いてあった。不思議に思っていたら「インキョクラモト」とも呼ぶという人がいた。
隠居というと、家業を息子に譲って昼間からお茶を飲んで庭木を眺めているような人や境地を言うと思っている人は多い。しかし江戸時代の上級武士では、病気や高齢を理由に家督(職と俸給)を嫡子に譲ることで、願いを出し認められると成立する。上記の他に不品行等で隠居させられる場合もあった。細かいところは幕府と各藩では違い、藩でも鳥取藩のように制度として無かった藩もあった。
驚くべきことに分家のことを隠居と呼ぶ人がいる。正確には親が次男三男などを連れて分家することである。紛らわしいので「隠居分家」と書いておこう。あるいは、次男が親を連れて分家しても見た目には同じことである。
かつて本連載第132回で、新屋のことを「にいや」と呼ぶ地域があることを書いたが、この隠居分家のことを「しんや」と呼ばず「にいや」と呼ぶと書いてあるものもある。同一漢字で意味の異なるものを異なって呼ぶ場合は、次第に曖昧になりわからなくなるのは当然で、一義的に考える必要はないと思う。それとも、中庄町の地区名・仁井屋はある家の隠居分家に因むのだろうか。
写真・文 柏原林造
関連記事
[ PR ] 瀬戸田で唯一の天然温泉
サンセットビーチの砂浜に面し、1,000坪の広大な敷地には、四季折々の花が咲き誇ります。部屋や温泉からは瀬戸内海に浮かぶ『ひょうたん島』と、美しい夕日を楽しめます。
素敵な旅のお手伝いができる日を楽しみにお待ちしています。
PRIVATE HOSTEL SETODA TARUMI ONSEN
瀬戸田垂水温泉
広島県尾道市瀬戸田町垂水58-1
☎ 0845-27-3137
チェックイン 16:00 〜 20:00
チェックアウト ~9:00