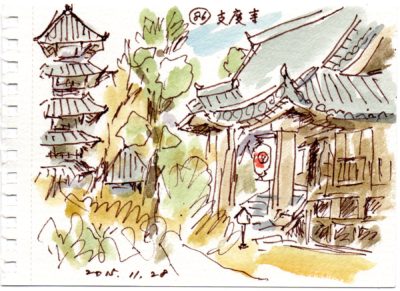父のアルバム【12】第三章 教師の信念
父が他界して17年が過ぎた。よやく父の人生を書く決心ができた。それにしても随分遅くなったものだ。本当は私がUターンし、父と同居している時期にその作業をすべきだったのである。にもかかわらず、私にはそれができなかった。
何故それができなかったのか。そしてまた、何故今、書くことを決心できたのか。父の人生を言及するにあたって、それらの理由を明らかにせねばならない。そうすることが、父への最低の礼儀であろう。
私の場合、父の人生を文章にすることは簡単なことではなかった。そのためには乗り越えねばならない高い壁が存在したのである。その壁とは時代の壁ともいうべきもので、ふたりの間には戦前と戦後という深くて大きな谷間があった。
父は明治末期に生まれ、大正と昭和を生き、敗戦を経験した。そして、戦後という時代を、自らを変貌させることで生き抜いた。とりわけ、教師でありつづけようとするならば、新たな時代への順応は不可欠であった。
敗戦直前に誕生した私はまるっきり戦後派であった。確かに明治・大正・昭和という近代史も学習した。しかし、自分が理解したその内容は、せいぜい知識としての歴史というものだった。したがって、その歴史のなかで生活する私の家族をイメージすることはなかった。
致命的であったのは、家族の戦争体験についての認識を共有できなかったことである。第二次世界大戦の末期、私の生まれ故郷は空襲を受け、私の生家は全壊し、母と祖母、そして生まれて間もない私はがれきのなかから救出されたのである。にもかかわらず、その事実を自覚しないまま私は育っていった。
いつのまにか私にとって、戦争とそれを生み出した戦前という時代は他人事になってしまった。戦前と戦時があって戦後があるという当たり前の歴史認識すらできなかった。その結果、戦前・戦時の家族の営みを切り捨てることになったのである。
やがて転機が訪れる。戦争末期に学徒動員された当時の大学生に会う機会を得た。私は質問した。
「どうしてあの無謀な戦争に行ったのですか。どうしても私にはその理由が分かりません」
相手の回答は明快だった。
「あの時代の雰囲気のなかではその気になった。君のような学生は当時ならきっと特攻隊に行ったよ」
「そうですか、私も特攻隊ですか」
その時の会話の情景を今でも忘れることができない。目からウロコである。不意打ちをくらって反論できなかった。やがて納得した。私は私の内面に初めて、戦前と戦時を意識した。学業半ばに散ってしまった特攻隊を身近に感じた。新しい問題意識がじわじわと芽生えて行った。
(青木忠)
[ PR ]瀬戸田で唯一の天然温泉
サンセットビーチの砂浜に面し、1,000坪の広大な敷地には、四季折々の花が咲き誇ります。部屋や温泉からは瀬戸内海に浮かぶ『ひょうたん島』と、美しい夕日を楽しめます。
素敵な旅のお手伝いができる日を楽しみにお待ちしています。
PRIVATE HOSTEL SETODA TARUMI ONSEN
瀬戸田垂水温泉
広島県尾道市瀬戸田町垂水58-1
☎ 0845-27-3137
チェックイン 16:00 〜 20:00
チェックアウト ~9:00