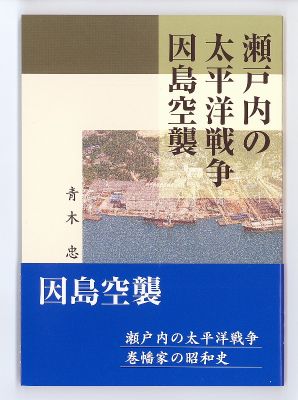亥の子まで炬燵の火入れ待つとするスイッチポンの電器なるとも
掲載号 08年11月22日号
前の記事:“市民劇団尾道てごう座 合併の垣根越え因島初公演 感動の余韻残した本因坊秀策伝”
次の記事: “ふたりの時代【22】青木昌彦名誉教授への返信”
白須 淑子
一首を目にして、炬燵の暖かさを待ちわびた少年期を懐かしみました。「炬燵は亥の子から」と聞かされたが、それが何月何日であるかは確定できなかったのです。当時は何事につけ、是非を問う前から慣例をよしとしていた様です。
ところで短歌の鑑賞・批評・吟詠といった場合にも似たような作法があるようです。
たとえば「草の実」という言葉に接したとき、発芽から結実までの過程を想定し、四季の変化、日常作業などをふまえ、解釈・鑑賞・批評などの短歌活動を進めるのも慣例どおりと言えるでしょう。
このような順応形の言葉に激しく反応する作家が新しい言葉を造り、新形式の短歌を発表したならどうでしょうか。
では新形式の短歌を見せよと迫られると私は困ります。造語でよいからと求められても同じことですが、造語なら部分的な事例なので大事件にはなりません。
歌人・斉藤茂吉は弟子と最上川を旅しました。その弟子が雨で逆巻く最上川を指さし「先生できました」と披露したのが『最上川逆白波の立つまでに…』だと伝えられています。それを聞いた途端、茂吉は弟子に「その逆白波を俺にくれ」と命じました。茂吉でさえ「未知なる新鮮」に翻弄されたのです。
結論を急げば、短歌のような表現芸術で大方の賛同を得るには、「未知なる新鮮」が求められますが、事を急がぬという慣例遵守も必要と感じています。
(文・平本雅信)