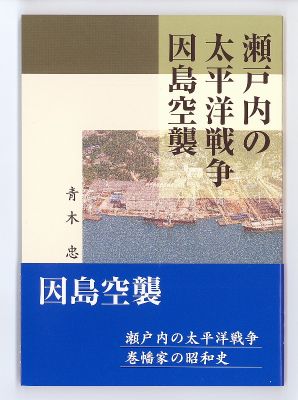ふたりの時代【17】青木昌彦名誉教授への返信
掲載号 08年10月18日号
前の記事:“山畑のセイタカアワダチソウは競うごとミカン木の間で風に揺れおり”
次の記事: “時代的背景を紡ぐ 本因坊秀策書簡【16】秀甫の運命(その5)”
伝説の60年安保 下
最近、「60年安保のころ何歳だった」と家内に尋ねたところ、「10歳で小学校5年かなあ、アンポハンタイ、アンポハンタイと言って遊んでいたことを覚えている」という返事がもどってきた。当時、彼女は埼玉県川越市に住んでおり、私は因島の高校1年であった。私はその記憶がなく、やはり国会までの距離の違いかな、などと思った。
安保闘争は最終局面を迎えようとしていた。当時早稲田大学の学生としてその渦中にあった評論家・蔵田計成氏は、「60年安保闘争辞典」のなかで次のように記している。
―60年安保闘争では改定安保条約自然成立の6月19日が近づくにつれて、20万人から30万人のデモ隊が国会目がけて連日津波のように押し寄せた。6月15日、全学連デモ隊1万人は「アイク休戦粉砕、岸内閣打倒、新安保阻止」をスローガンに国会南通用門から構内に突入した。警官隊は警棒で襲いかかり多数の重軽傷者を出し、東大女子学生・ブンド同盟員樺美智子が虐殺された。この6・15闘争に対しては全国津々浦々に共感の波が広がり、警官の暴虐と岸内閣の暴挙に対する憤激の嵐の中で内閣は倒された。
青木昌彦氏は、この政治過程に著書のなかで次のような評価を提起している。
―ともかく岸首相は最後に自衛隊の動員まで考え、防衛庁の長官に断られたそうだが、ブンドにはさらなる激烈な運動を組織する余力はなく、6月19日に安保条約の改定は国会で自然承認された。岸首相はそれを持って退陣し、大衆運動は潮を退くように鎮まった。これでブンドは敗北したというのが、ブンドの「正当史」だ。だが負け惜しみではないが他の見方もあり得るのでないか、と私は思う。安保闘争を画期として、国のかたちをめぐるゲームのあり方が変わったといえるからだ。
つまり一方では、自らの民主的な統治能力の不足を国家の軍事力の動員によって補うというような、岸流の政治的選択に未来はなくなった。その後の経済成長をリードした経営者のあいだにさえ、安保闘争によって統制経済復活の可能性の重しがとれたことを評価する人が数少なくないと聞く。
それにつづけて注として、元野村證券会長田淵節也氏の次の文章を引用している。
―青木昌彦さんの履歴書を面白く読んだ。僕は共産主義とは反対の人間だが、60年の「日米安全保障条約」が象徴的な出来事だったと見る点で共感した。時の岸信介首相は旧満州国を統治した国家資本主義の手法で戦後の日本を統治しようとした。
さらに政治運動について、次のように述べている。
―他方では、民衆の自発的な政治行動を統制し、管理するという「前衛党」神話や、労働者階級が暴力によって国のかたちを変えるために立ち上がるという幻想も打ち砕かれた。それ以後、政府は高度成長の果実を用いて、さまざまな利益団体の要求を順次取り込み、多元的な利益を裁定しながら政治的安定を図っていく、左翼政党もそういうメカニズムの一翼を担っていく、そういう時代になった。