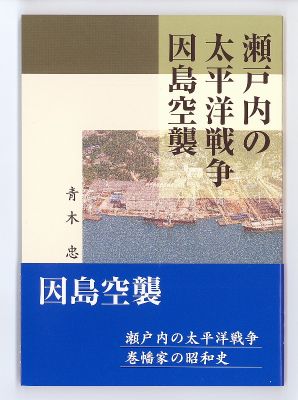ふたりの時代【7】青木昌彦名誉教授への返信
掲載号 08年08月02日号
前の記事:“時代的背景を紡ぐ 本因坊秀策書簡【8】NHK大河ドラマ「篤姫」と囲碁(その八)”
次の記事: “8月6日にお参り続く瀬戸田町の原爆慰霊碑”
まさかの縁(下)
椋浦町は予想だにしなかった人生上の大逆転の場になってしまった。全学連や政治闘争から逃亡するために生まれ故郷の瀬戸内海の島、そのなかでもここだけは大丈夫と思ったその場所に住み着いた故にこそ、全学連や60安保闘争に再会するとは、誰が想像しえよう。帰ってきて17年も経てば、島の住人になりきったと言ってもいいだろうに。
故郷の、ある世代以上の人たちは、私の過去をなんらかの形で知っており、私も、それを隠したり、ことさら喋ったりすることはしない。妻には最近になってポツリポツリと説明をしだしたのだが、娘や息子には私自身についてほとんど語っていない。いつかは、子どもたちに尋ねられれば、語るときがくるだろうとは思っていたが、過去の出来事を白日のもとにさらけ出すときがやってこようとは、夢にも思わなかった。
青木昌彦氏の日本経済新聞「私の履歴書」への華麗な登場と、それにつづく、「私の履歴書 人生越境ゲーム」という挑発的なタイトルの本の出版は、まさしく予期せぬ台風であった。隠れ家は吹き飛ばされ、まるでお白州に引きずりだされてしまった格好になった。
その著作の人名索引を見てまた、驚かされた。わたしの名が、60年安保闘争時の米国大統領アイゼンハワーにつづいて二番目に示されているではないか。さらに「あとがき」で著者がお礼を述べるくだりでも、私が冒頭に来ている。それが形式の順番であることを充分承知したうえでも、「意図性」を感じざるをえず、もはや後戻りできない何かを感じた。
やがてわが家に、「社学同(社会主義学生同盟)の篠原です」などという、とんでもない電話が入った。社学同とは60年安保闘争を担った学生組織である。その応対に戸惑っている私に篠原浩一郎氏は平然と、出版祝賀会の呼びかけ人になってくれないかと、言い放つのである。思わず「私のような者で大丈夫なのでしょうか」と、拒絶したことは言うまでもない。しかし、初めて会話する年輩者の篠原氏はなかなかの曲者で、まるで赤子の手を捻るがごときの容易さで、殺し文句を吐くのだ。「いえいえ、どういたしまして。著者の青木本人のたっての希望ですから」と、すべてを推し量ったうえで、切り込んできた。そう言われれば断れるはずがないではないか。
神経質なくせにのんびり屋でもある私ではあるが、ここまでくると事態がのみこめてきた。そればかりか、これは60年安保闘争世代からの挑戦状ではないのか、よし受けて立とうとさえ、思った。チャンス到来でもあった。青木昌彦氏の力をお借りして、まさに便乗して、私の青春そのものであった、60年安保闘争から70年安保闘争の時代を、まるで大学生にまで成長したわが子に語りかけるような作品にしてみようと思った。
私の因島での生活は、まるで「鎖国」の状態であった。島に閉じこもり、島を城として、外界と交渉を断つことで自己と生活の再確立をめざした。そして、その永続化さえ目論んだ。時たま訪れる外界からの便りを無視することにも何の躊躇い(ためらい)も感じなくなっていた。
青木昌彦台風は黒船襲来だったのか。無駄な抵抗はやめて、あっさりと「開国」に転じることにした。自宅を事務所にすることにした。原則、どなたでもおいでくだいさい、というわけだ。いまやわが家は千客万来である。全国から電話、メールが頻繁に入ってくるようになった。20年もの間、絶えていた交信も徐々にではあるが、回復しつつある。20代をはじめ、様々の報道機関の若き記者たちが、取材に訪れるようになってきた。
椋浦町は不思議な町だ。もはや行き場のなくなった壮年の男に生活の場を与えたばかりか、人生の大逆転のチャンスを提供し、再起を期す跳躍の場になっている。