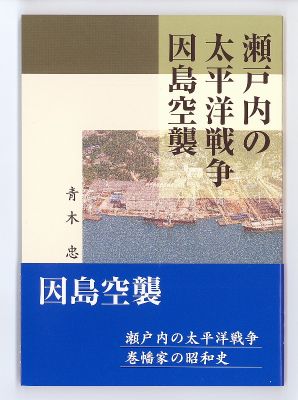空襲の子Ⅱ【完】十年間の調査報告 辿りつきしところ(4)
掲載号 13年03月30日号
前の記事:“福島放射能汚染地域に生きる子どもたち【6】”
次の記事: “続・井伏鱒二と因島【11】その作品に表現された「因島」”
妻と語り合った。私は尋ねた。
「きみが生後まもなく養女に迎えられたのはいつごろのことだったのかな」
彼女はこともなげに答えた。
「生後1年3カ月のころと聞いているわ。埼玉の浦和市の児童相談所から呼び出しがきて、まだ分からない年齢の時にということで、すぐ話はまとまったみたいよ」
妻の出身家族は、1944年3月10日の東京大空襲の焼夷弾で葛飾区亀戸の自宅もろとも母と娘の3人を失った。
父と山形に疎開していた3女は生き残った。父・宗一は満と再婚し、2人の娘を産んだ。その下の子が妻で、昭和25年1月誕生。出生地は東京都江戸川区である。
戦後の窮乏はこの家族を容赦なく襲った。両親は飢餓より、乳離れして間もない妻を養女に出すことを選んだ。埼玉県川越市の子供のいない夫婦が暖かく迎えた。後継ぎとして自らが産んだ子のように可愛がった。
私の質問はつづく。
「いつごろ知ったの、養女であることを」
「小学生のころかな。お転婆の私が近所の男の子と喧嘩すると『もらいっ子』と言い返された。大人の陰口も聞こえてきた。でもその意味が理解できず、とくに傷ついたりはしなかったよ」
「ふーん、それから……」とつづきを求めた。
「中学生になってからかな、その意味が分かってきたのは。だけど、くよくよはしなかったよ。『だから何だっていうのよ』という調子だったわ。高校入学時に戸籍謄本に『続柄 養女』とあるのを見て矢張りそうだったのかと思ったが動揺はしなかったわ」
妻は今でも、川越の養母しか母親と思えないという。生母は写真で見るひとりの女性でしかないとも語る。
やがて養母の心遣いでふたりの姉と会うときがやってきた。妻はすでに30歳を過ぎていた。このとき産みの親はふたりとも他界していた。姉妹3人そろって千葉県松戸市にある都立八柱霊園にある墓に参ることができた。
私はくどいとは思ったが、
「生んでくれた母親のことを考えることはないのか」と訊いた。
彼女は素直な心象を言葉にした。
「生みの母親と言われてもピンとこないのよ。やはり捨てられたという想いが消えないのよね」
生母についてのふたりの感じ方の違いに気付いた。強く追い求める私に対して、あまり執着してないように見える妻。これは決して議論する問題ではない。しかし私は、彼女が戦争体験を内在しながらも、戦後を明るくたくましく生き抜いたひとりであることを実感した。
連載の最後に生母と祖母、妻のことを記した。これらすべてが結局のところ私が辿りついた自らの精神の原点だろうと思う。私はあのとき一度は死んだのだ。そして違う人間として生まれ変わったのだ。どうしてもそうした潜在意識から抜け出せないでいる。
生まれ変わった私は、それにふさわしい生きざまを示しえたのか。あまりに虚しく、あまりに淋しい。叶うことなら、小説という方法でもよいから、もう1回白紙から生き直してみたい。それができるならどんなに幸せなことであろう。
(青木忠)
新連載「小説ぼうし」青木忠氏の新連載「小説ぼうし」が4月13日号からスタートします。同氏にとって初めての小説の執筆になります。