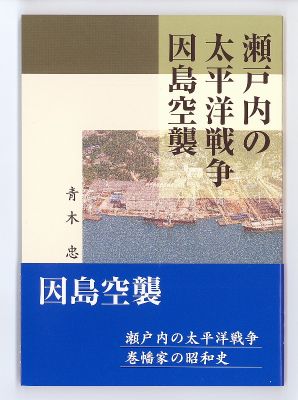空襲の子【30】因島空襲と青春群像 62年目の慰霊祭 小丸正人さんに捧ぐ(下)
掲載号 07年03月31日号
前の記事:“盛り上がりに乏しい県議選”
次の記事: “尾道市定期人事異動を発表 因島総合支所長に田頭敬康氏 瀬戸田支所長に相原満氏”
その日、長女・由紀子さんは戸板で運ばれる人を土生町で見た。土生の祖父のところに行かされていたのだろう。もちろんそれが、父であるかどうかは分らなかった。亡骸が自宅に着いたのは夕方のころ。仏壇の前に横たわる夫は死んだとは思えないほどきれいだった。それが、妻・コミヱさんにはよけいに悲しかった。
ふたりの娘は振袖姿で葬儀に臨んだ。幼い祥子さんは「白い着物をきてお父さんどこへ行くん」と母に聞いたという。気丈にふるまっていたコミヱさんは涙がこらえきれなくなった。娘に母が後になって語って聞かせた。
大八車に乗せられて父は竹長の火葬場に向かった。遺体を見ることができなかった由紀子さんが、再び会ったのは骨だけになった父であった。小さくなってしまったと感じた。
小丸家に終戦が訪れた。父が死んだのは、そのわずか19日前のことである。戦後が始まった。どの家族も例外なく苦難の日々がはじまった。とりわけ大黒柱を失った家族にとってはそうであった。父が生き残っている家庭であれば、父の働きを中心に生活の安定がやがてもどってくる。父を空襲で失い残された者は苦難の日々からの脱出が容易ではなかった。
空襲の犠牲者は戦死ではなかった。公的な支援は受けられない。軍人・軍属には、戦死を前提にした恩給制度があった。民間人には空襲での犠牲を救済する制度はない。原爆の被爆者は強い要求で国を動かし、被爆者援護法を制定させた。
小丸家の戦後は、貧しかった。どん底の食糧難であったという。さつま芋は供出。外米、ジャガイモ、カボチャ、麦、とにかくおいしくなかった、と由紀子さん。亡き夫の墓をつくれず遺骨を親類の墓に入れさせてもらったときは本当に辛かったと、コミヱさん。
現在もつづいている駄菓子屋を始めたのは昭和24年のこと。中国電力の集金の仕事も生活を支えた。2人の娘も戦力だった。近所ではあったが、娘たちは夜8時、9時まで町内をまわった。生きて行くために形振りかまってはおれない。
「困る(小丸)、困る(小丸)、大困る(おう小丸)、家は貧乏で大困る(おう小丸)」。これは「困る」と「小丸」をかけた、からかい歌である。通学路でもある駄菓子屋の前を通る小学生や中学生が歌った。今でも忘れられないと、3人は語る。コミヱさんは「腹がたって追いかけて捕まえてやろうか」と思ったと言う。
父がいないということは就職に絶望的なほど不利だった。日立造船も例外ではなかった。由紀子さんは同社への就職を希望したが、叶わぬ夢だった。父が働き空襲によって殉死した工場はその娘を迎えることをしなかった。悔しかった。でも仕方がなかった。
筆者は小丸家への取材を通じて、わたしの生きた戦後と違うもうひとつの戦後を生きた家族がいることを知った。わたしはどちら側だったのだろう。あの「からかい歌」を歌う子どもたちの一員だったかもしれない。「空襲の子」であることを知らされないまま成長した。初めて知ったときに感じたあの恥じらいはいったい何だったのだろう。

若き日の妻・コミヱさん