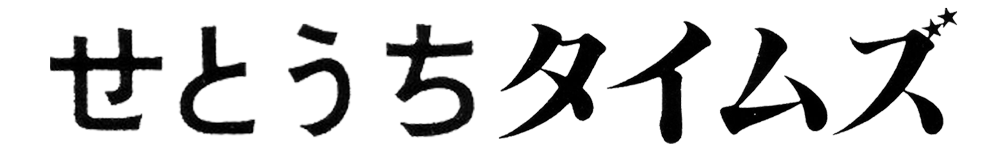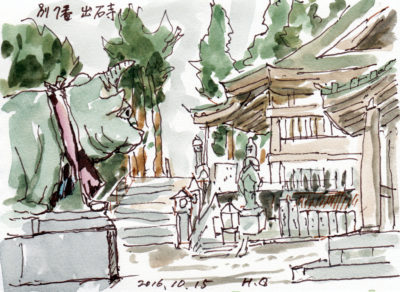父のアルバム【38】第五章 苦難を越えて
父にとって10年4カ月間の椋浦時代は、教師としての円熟期だったのではないだろうか。その後、2年間他校の校長を務めたが教育委員会に移り、教育現場から去った。
椋浦小学校百周年記念誌への寄稿文に父は、
「椋浦教育の道を求めて、戦後の回復と複式教育の基盤作りに七カ年、へき地教育の充実推進に三カ年を費やした」と記している。さらに「椋浦学校史」発刊に、「椋浦教育は今も生きている」という文章を寄せている。
当時の椋浦は「因島のチベット」とも呼ばれ、他地域とは昔のままの険しい峠道などでしか結ばれておらず、日常的な交通手段を巡航船の定期便に依存していた。そうした環境での教育にこそ父は燃え立ち、脇目も振らずそれに没頭したのである。
とは言え、この期間の父の奮闘振りを理解していたのは妻の行(ゆき)のみで、兄や姉にはそこのところが評価されてなかったようだ。
とりわけ、ふたりの姉は酷評するのである。
長姉は、「家の仕事が忙しい時なんか、お父ちゃんに『女は高校に行かんでええ』とまで言われた」と、高校時代のエピソードを私に語って聞かせた。
次姉も同様に厳しかった。
「お父ちゃんはよその子供の世話に一生縣命なくせに、自分の子供には何もせんのよ」が口癖だった。
ふたりの兄からも父をほめた言葉を一度も聞いたことがなかった。
私の父への印象は少し違っていた。父たちの「椋浦教育」に影響を最も受けたようだ。そのためか、私の学校教育像の根っこには6年間通った椋浦小学校体験がある。
しかし、「校長の息子」という世間的な縛りが私を窮屈にさせた。当然にも、ふたりの自分を使い分けようとするようになった。「良い子」と「そうでない子」である。
小学校のころを回想すると真っ先に思い出す歌がある。それは春日八郎の「お富さん」である。
粋な黒塀 見越しの松に
仇な姿の 洗い髪
死んだ筈だよ お富さん
生きていたとは お釈迦さまでも
知らぬ仏の お富さん
エーサオー 玄治店(げんやだな)
この歌が発売されたのは1954年(昭和29)8月で、私は小学校4年だった。大ヒットし、小中学生ばかりか、幼児までが歌いだす始末で、「お富さん」は社会現象にまでなってしまった。
(青木忠)
[ PR ]ピザカフェつばさ
みょーんと伸びるチーズとこだわりの生地を溶岩石窯で一気に焼き上げます。
テイクアウト歓迎。
尾道市因島土生町フレニール前(旧サティ因島店前)
TEL 0845-22-7511
平日・土曜日 11:00~22:00
日曜日・祝日 11:00~14:00